BACK TO DINOPIX GALLERY
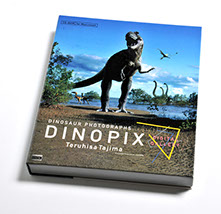

1992年の秋に、ぼくはアメリカの小さな田舎町モアブを訪れた。分からない何かがぼくを付き動かそうとしていたのである。自分の中の未整理な部分の何かがいつも気がかりで、年齢的なクライシスなのか、そろそろ決着を付けたいと焦りかけていた。ユタ州、アーチーズ国立公園の早朝。平原の遥かずっと向こうのオレンジ色の朝モヤのなか、夜行性のラプトルたちが白い息を吐きながら家路を急ぐ姿を見た。朝陽を浴びて赤味を増した巨大な岩肌に、ブラキオサウルスがそのカミナリ竜特有の長い首の影を落としているのを見たような気がしたのだ。少し掴みかけようとしているこれらの答えを目のあたりにしても、あまり焦ることはしなかった。この先、そんなシャッターチャンスは十分過ぎるほどに用意されていそうな気がしたからだ。
去ること5年ほど前に偶然訪れたアルバータ州バッドランドのタイレル・ダイナソウ・ミュージアムで、太古の巨大生物たちの骨格標本を見上げながら、ぼくはある再生のシナリオのヒントを無意識に得ていた。白状すると誰よりもぼく自身が、こんな写真を待ち望んでいたのだ。ずっとむかし、少年だった頃に誰もが思うように、この未知の巨大生物たちをこの目で実際に見てみたいと思っていた。どこかにまだ居るのかもしれない、生きているうちに見ることは可能だろうか、彼らはいったいどんなふうに見えるものだろう、運よく彼らに遭遇できたら、絶対に写真に撮ってやるのだと。判ってはいても、近代の情報量の多さは、無粋にもそんなものが生息している可能性が少ないことを示していた。そしてイギリスの細長い湖で最後の可能性が限りなくゼロに近付いてしまった今、そろそろこの日常の見慣れた風景を一転させてみるのも悪いことではないような気がした。
モアブでぼくの網膜だけに焼き付けられた巨大生物たちの再現には慎重を帰した、ぼくはどうしてもあの時の幻影をいかにして具現化するかにこだわった。そしてそれらを蘇らせるひとつの方法論は、目の前のブラウン管の中にあることも知っていた。とても安易なことだけれど、流行りのデジタル回路を介在することで、望むところのファンタジーがいとも簡単に訪れるのだとしたら?しかしこの巨大生物たちの再生にはなによりも生きている力のようなものが必要だった。ずっと前から玄関に飾られていた海洋堂の精巧なフィギュアは、それを可能にしてくれそうな気がして、思い切ってぼくはアナログの世界で造られたそのフィギュアに、自然の光を与え、デジタル回路を通して皮膚に湿度を加え、筋肉の緊張や弛緩を増長し、視力と咀嚼力を与え、そして百倍に拡大しても生きているような生物の再生を試みた。納得のいく回答ではなかったが、手ごたえは充分にあった。いずれにしても最初にこのブラウン管の中に突如として出現した巨大生物は、可能性と勇気をぼくに与えてくれたのだ。
1994年5月 田島照久